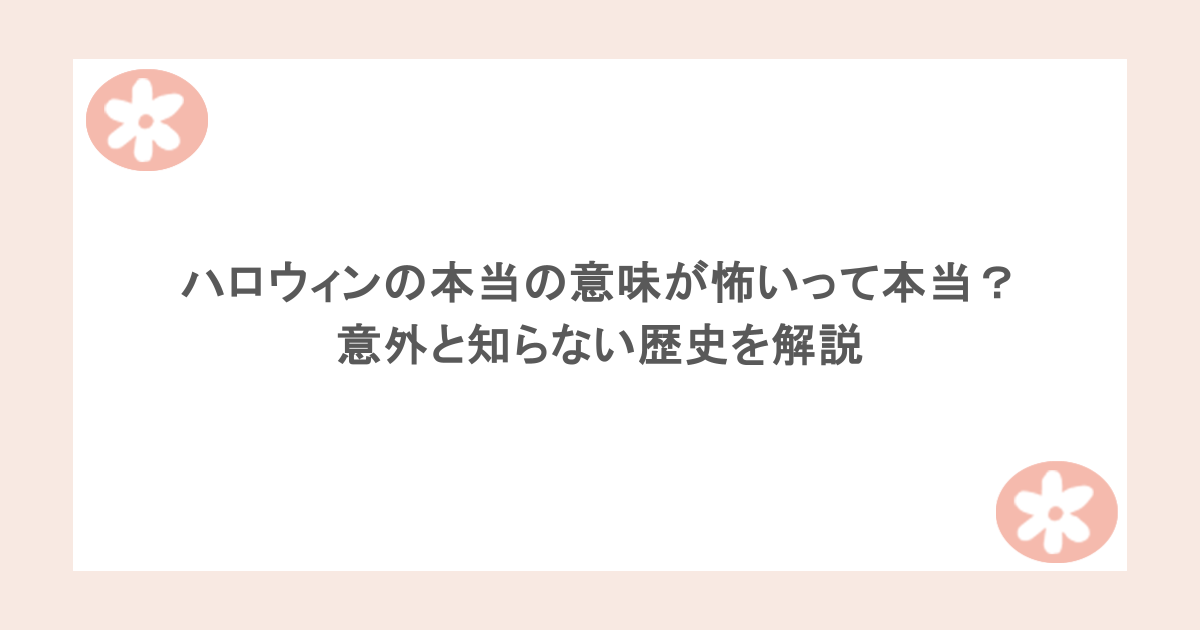ハロウィンの本当の意味が怖いといわれているのをご存知ですか?
ここ数年で、ハロウィンは日本でもすっかり秋の定番イベントになりましたね。 しかし、その本当の意味を知ると、ただ楽しいだけのお祭りではないかもしれません。
この記事では、意外と知られていないハロウィンの歴史や、「怖い」と言われる本当の意味について、詳しく解説していきます。
ハロウィンの本当の意味が「怖い」と言われる理由

ハロウィンの本当の意味が怖いといわれているのは、ハロウィンがもともと「死者の魂が帰ってくる日」だからと言われています。
死という概念が絡むと、途端に未知で恐ろしい雰囲気を醸し出しますよね。
ハロウィンで行う仮装に、お化けやモンスターといった怖い見た目のものが多いのも、このイメージが影響しているようです。
この世とあの世が繋がり悪霊がやってくる
ハロウィンの起源とされる古代ケルトの文化では、10月31日はこの世とあの世の扉が開く日だと信じられていました。
亡くなった家族の魂が帰ってくるのは、日本のお盆にも似ていますが、ハロウィンで怖いのは、良い霊だけでなく、悪魔や魔女といった悪霊も一緒にやってくると考えられていた点です。
悪霊から身を守るための「仮装」
悪霊たちは、生きている人間を見つけると、魂を奪ったり、あの世へ連れて行こうとしたりすると恐れられていました。
そこで古代の人々は、悪霊の仲間だと思わせて身を守るために、あえて怖いモンスターやお化けの格好をするようになったのです。これがハロウィンの仮装の始まりなんですね。
つまり、ハロウィンの仮装は、もともとは悪霊から身を守るための「魔除け」の意味合いが強かったのです。
意外と知らないハロウィンの歴史を深掘り!
それでは、ハロウィンの歴史についてさらに詳しく見てみましょう。日本で人気の仮装パレードや「トリック・オア・トリート」の背景には、2000年以上も前の古い歴史が隠されています。
【参考サイト:PREZO】
起源は古代ケルト民族の「サウィン祭」
ハロウィンの起源は、紀元前にヨーロッパに住んでいた古代ケルト民族のお祭り「サウィン祭」だといわれています。
古代ケルトでは11月1日が新年とされており、その前夜である10月31日は、日本でいう「大晦日」にあたる大切な日でした。この日に、秋の収穫を祝い、亡くなった家族の魂を迎える盛大なお祭りとして「サウィン祭」が行われていたようです。
「ハロウィン(Halloween)」の語源とは?
「ハロウィン」という言葉の語源は、キリスト教の祭日「万聖節(ばんせいせつ)」からきています。
万聖節は「諸聖人の日」とも呼ばれ、すべての聖人を祝う11月1日のことです。 英語では「All Hallows’ Day」と表記され、その前夜祭である10月31日は「All Hallows’ Eve」と呼ばれていました。
この「All Hallows’ Eve」という言葉が少しずつ変化して、現在の「Halloween(ハロウィン)」になったといわれています。
新年・お盆・秋の収穫を一度にお祝い!
ハロウィンは、当時の新年だった11月1日の前夜に収穫を祝い、同時に死者がやってくる日でもありました。
これは、日本でいうところの3つのイベントが一度にやってくるイメージですね!
| 日本の行事の例 | ハロウィンの要素 |
| 大晦日 | 1年の終わりと新しい年の始まりを祝う |
| お盆 | 亡くなったご先祖様の魂が帰ってくる |
| 秋祭り | その年の収穫に感謝する |
情報量が多くて少し混乱するかもしれませんが、ハロウィンはこれだけ多くの意味を持つ、とても重要なお祭りだったんですね。
ハロウィンのシンボルに隠された本当の意味
ハロウィンといえば、「仮装」「かぼちゃのランタン」「トリック・オア・トリート」がおなじみですよね。 実は、これらのシンボルにも、それぞれに由来や意味が隠されています。
なぜ仮装するの?【怖い悪霊から身を守るため】
先ほども触れましたが、ハロウィンで仮装する理由は、悪い霊から身を守るためです。
死者の世界からやってくる悪魔や魔女たちに、人間だと気づかれないように同じ姿に扮したのが始まりで、今でも魔女や悪魔の仮装は定番となっています。
1950年代にアメリカでホラー映画が流行してからは、フランケンシュタインやドラキュラといったモンスターの仮装も定着しました。
もちろん、現代では本来の意味合いは薄れ、アニメキャラクターなど好きな格好で楽しむイベントになっていますね!
かぼちゃのランタン「ジャック・オー・ランタン」の怖い由来
ハロウィンのシンボルといえば、不気味な顔をくり抜いたかぼちゃのランタン「ジャック・オー・ランタン」ですよね。このランタンには、アイルランドに伝わる少し怖い物語が由来となっています。以下では、おおまかなあらすじをご紹介しますが、気になる方は次の動画も参考にしてみてください!
出典元:今さら聞けない【ハロウィーン】って何? 不気味なカボチャ「ジャック・オ・ランタン」の正体をスピード解説!トリックオアトリートの本当の意味とは?(Halloween / Jack-o’-Lantern)
ジャックという男の物語(おおまかなあらすじ)
- 生前、悪さばかりしていたジャックという男がいた。
- ジャックは悪魔を騙し、「自分の魂を地獄に落とさない」という契約を結ばせる。
- 死後、ジャックは生前の悪行から天国へは行けなかった。
- しかし、悪魔との契約があるため、地獄へ行くことも拒否されてしまう。
- 行き場をなくしたジャックは、悪魔からもらった火種をカブの中に入れてランタン代わりとし、今も永遠に暗闇をさまよい続けている…。
この物語から、ジャック・オー・ランタンは「さまよえる魂の象徴」とされ、同時に悪霊を追い払う「魔除け」の意味も持つようになりました。ちなみに、もともとは物語の通り「カブ」で作られていましたが、この文化がアメリカに伝わった際、手に入りやすかった「かぼちゃ」が使われるようになり、それが定着したそうです。
「トリック・オア・トリート」の本当の意味
「トリック・オア・トリート」は、「お菓子をくれないと、いたずらしちゃうぞ!」という意味でおなじみですね。
この風習の由来は諸説ありますが、もともとは、ハロウィンの日に子どもたちが仮装して家々を回り、死者の魂のために祈る代わりにケーキをもらって歩いたという中世の習慣が元になっていると言われています。
「トリック・オア・トリート」という言葉自体は1920年代に生まれ、1950年代頃にアメリカで定着したとされています。
【国別】世界のハロウィンはこんなに違う!
ハロウィンは発祥の地アイルランドから世界中に広まり、各国の文化と融合して独自に発展しています。 ここでは、国ごとの特徴的なハロウィンの楽しみ方を比べてみましょう。
| 国 | 特徴的な楽しみ方 |
| アイルランド | 【発祥の地】 ・伝統的なお祭りが今も続く ・運勢を占う「バームブラック」というパンを食べる習慣がある ・世界最大級のパレードも開催される |
| アメリカ | 【子どもが主役】 ・子どもたちが仮装して「トリック・オア・トリート」と近所を回るのが一般的 ・家をホラー風に飾り付け、盛大なパーティを開く家庭も多い |
| メキシコ | 【死者の日】 ・ ハロウィンと融合した「死者の日」というお祭り ・ガイコツの仮装をし、祭壇を飾って死者の魂を迎える ・日本のお盆に近いが、明るく盛大に祝う |
| イタリア | 【お盆に近い】 ・「死者の日」があり、多くの人が教会へ行きお墓参りをする ・イベントというよりは、静かに故人を偲ぶ日という側面が強い |
| 日本 | 【大人が主役の仮装イベント】 ・「トリック・オア・トリート」はあまり根付いていない ・若者や大人が中心となって仮装やパレードを楽しむイベントとして定着している |
まとめ
今回は、ハロウィンの本当の意味や、意外と知られていない怖い歴史について解説してきました。
ハロウィンの起源を知ると、ただの仮装イベントではなく、悪霊から身を守るための切実な儀式だったことがわかりますね。
歴史的な背景を知ることで、ハロウィンがより一層奥深く感じられるのではないでしょうか。この記事を参考に、ぜひ今年のハロウィンをもっと楽しんでみてくださいね!